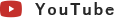- HOME >
- 高校生の現代文テスト対策 大岡昇平『俘虜記』②
高校生の現代文テスト対策 大岡昇平『俘虜記』②
ひきつづき第2回として、『俘虜記』の作者大岡昇平の強く意図したところであり、そして現在も高校生の『現代文』の教科書にこの作品が掲載されている大きな理由だと思われる、局地的な敗北が確実であり、すなわちその場にあった兵士たちの死もほぼ確実だったであろう極限の状況下の記憶を振り返り、その時の心理を分析した、米兵との近い距離での遭遇の場面を見て行きます。
なお、『俘虜記』の執筆動機の根底に近いものと思われる、この心理描写については、作品中、件の米兵がふたたび作者の前に姿を現したことが語られる、その直前の部分に、次のように記されています(以下、引用のみの部分は< >でくくります)。
<これが我々が心理を見詰めて見出し得るすべてである。>
では、作者の前に米兵が登場した場面の少し前から、順に見て行きましょう。
<確かなのは私が米兵が私の前に現れた場合を考え、それを射つまいと思ったことである。
私が今ここで一人の米兵を射つか射たないかは、僚友の運命にも私自身の運命にも何の改変も加えはしない。ただ私に射たれた米兵の運命を変えるだけである。私は生涯の最後の時を人間の血で汚したくないと思った。>
この時点では、まだ実際に会敵する前、「自分が米兵を射ったとしても、いずれ死を迎えるという、日本軍の僚友(上官を含めた友軍将兵)の運命も、自分の運命も変わらない。ただ自分が射った一人の米兵が命を失うかどうか、それだけだ」という考えから、米兵に遭遇しても発砲すまいと、考えていたのです。さらに米兵と行き会ったら、自分は射たずに相手から射たれ、倒れた自分の傍らに相手が駈け寄る、という想像のうちに、「この最後の道徳的決意」を「人に知られたい」という望みがあったのだと言います。
ところが実際に米兵が現れると、<私は果して射つ気がしなかった。>としながらも、多面的に動く心理状態が詳細に描写されます。
<私は異様な息苦しさを覚えた。私も兵士である。私は敏捷ではなかったけれど、射撃は学生の時実弾射撃で良い成績を取って以来、妙に自信を持っていた。いかに力を消耗しているとはいえ、私はこの私が先に発見し、全身を露出した相手を逸することはない。私の右手は自然に動いて銃の安全装置を外していた。>
<私は溜息し苦笑して「さて俺はこれでどっかのアメリカの母親に感謝されてもいいわけだ」と呟いた。>
<まず私は自分のヒューマニティに驚いた。私は敵を憎んではいなかったが、しかしスタンダールの一人物がいうように、「自分の生命が相手の手にある以上、その相手を殺す権利がある」と思っていた。従って戦場では望まずとも私を殺し得る無辜(むこ)の人に対し、容赦なく私の暴力を用いるつもりであった。>
実際に若い米兵が現れた時、作者はその敵を射とうと思わず、最終的にも射たなかったのです。ただ、前回も述べた通り、作者は射撃には自信があり、無防備に身をさらしている一人の米兵については、射とうと思えば射てたと考えていました。また、スタンダールの小説『パルムの僧院』に登場する「モスカ伯爵」の「自分の生命が相手の手にある以上、相手を殺す権利がある」という言葉の通り、戦場で相手に自分の生死が握られているならば、自分の力でその敵を倒すつもりでいたとも、述べています。
ただ、「モスカ伯爵」のマキャベリズム*1は、「殺されるよりは殺す。」ということであり、自分の命を守るために相手を殺す、という論理です。しかしこの時、作者はすでに、自分の命が近々断たれるものと考えていたのです。
<この時私に「殺されるよりは殺す」というシニスム*2を放棄させたものが、私が既に自分の生命の存続について希望を持っていなかったという事実にあるのは確かである。明らかに「殺されるよりは」という前提は私が確実に死ぬならば成立しない。
しかしこの無意識に私の裡に進行した論理は「殺さない」という道徳を積極的に説明しない。「死ぬから殺さない」という判断は「殺されるよりは殺す」という命題に支えられて、初めて意味を持つにすぎす、それ自身少しも必然性がない。「自分が死ぬ」から導かれる道徳は、「殺しても殺さなくてもいい」であり、必ずしも「殺さない」とはならない。>
自分の死は確実である。であるならば、「殺されるよりは殺す」という論理は成り立たない。しかし「自分が死ぬ」ことは、相手を「殺さない」ことの必然的な理由とはならない、という意と読みとれます。そして連続する次のくだりで、「殺さない」ことを選んだ過程が明らかにされています。
<かくして私は先の「殺されるよりは殺す」というマキシム(東京書籍版『現代文』の教科書では「命題」)を検討して、そこに「避け得るならば殺さない」という道徳が含まれていることを発見した。だから私は「殺されるよりは」という前提が覆った時、すぐ「殺さない」を選んだのである。>
つづいて、人を殺すことへの「嫌悪」についての考察が書かれています。そして「戦場」では、そうした「嫌悪」は存在しえず、すでに作者がまったくの「独り」であったからこそ、「平時の感覚」による「嫌悪」によって、「射つまい。」という決意がなされたのだと言います。
<要するにこの嫌悪は平時の感覚であり、私がこの時既に兵士でなかったことを示す。それは私がこの時独りであったからである。戦争とは集団をもってする暴力行為であり、各人の行為は集団の意識によって制約乃至(ないし)鼓舞される。もしこの時僚友が一人でも隣にいたら、私は私自身の生命の如何(いかん)に拘らず、猶予なく射っていたろう。>
さらにその「決意」が実現されたかどうかに、考察はすすみます。結果としては、作者とその間近にいた米兵が対峙することはなく、「他方で銃声が起こり、米兵が歩み去ったという」「一つの偶然」により、作者が「決意」を実現したか否かを証する「行為」は、完成されませんでした。しかし作者は、さらにどこまで「決意」が「行為」に影響したかを、検証しています。
<最初彼の姿を見た時、私は射つ気が起こらなかった。これは確かである。時間的順序から見て私はこれがその前にしていた決意の結果だと思っていた。しかしこれはそれほど確かだろうか。少なくとも私の心理にはそれを保証する何ものもない。>
「最初彼の姿を見た時」は、時間的には、先に引用した、「さて俺はこれでどっかのアメリカの母親に感謝されてもいいわけだ」と考えた時点にあたります。しかし記憶している映像から心理をさぐって行くと、それが事前の決意のためだったとは言い難い、という流れに、すすんで行くのです。
<私は私の前に現れた米兵の露出した全身に危惧を感じ、その不要心に呆れた。この感想は頗(すこぶ)る兵士的のものであり、短い訓練にも拘らず私がやはり戦う兵士の習慣を身につけていたことを示している。この感想の裏は「この相手は射てる」である。
しかも私は射とうと思わなかった。しかしこれは果して事前の決意の干渉のためだったろうか。もし私が戦闘意識に燃えた精兵であったとして、果してこの優勢な相手(私の認知しただけでも一対三である)を直ちに射とうとしたであろうか。
この瞬間の米兵の映像から私の記憶に残った一種の「厳しさ」は、私の抑制が私の心から出たものではなく、その対象の結果であった証拠のように思われる。それは私を押し潰そうとする膨大な暴力の一端であり、対するに極めて慎重を要する相手であった。この時私の抑制が単なる逡巡にすぎなかったのではないかと私は疑っている。>
ここでは、少なくとも敵が3名いて「一対三」であること、さらに米兵の印象の「厳しさ」が、自身の存在を押し潰そうとする暴力の一部であって容易ならぬ相手であると感じたこと、それゆえ射たなかったのは「逡巡(ためらい迷うこと)」によるものではなかったかと述べています。
さらに、米兵は若く、異人種の持つ一種の美が認められ、新鮮さを感じさせたこと、それが「敵前にある兵士の衝動を中断した」=兵士として倒せる敵を射つ行為を起こさせなかったようだ、という分析のあと、米兵の「若さ」に対する記述となります。
<私がこの米兵の若さを認めた時の心の動きが、私が親となって以来、時として他人の子、あるいは成長した子供の年頃の青年に対して感じるある種の感動と同じであり、そのため彼を射つことに禁忌を感じたとすることは、たぶん牽強付会にすぎるであろう。しかしこの過程は彼が私の視野から消えた時私に浮かんだ感想が、アメリカの母親の感謝に関するものであったことをよく説明する。明らかにこれは私がこの米兵を見てから得た観念である。その前私が射つまいと決意した時、私の前にどういう年齢の米兵が現れるかは不明であり、私が母親について考慮する根拠は全然なかったからである。
人類愛から射たなかったことを私は信じない。しかし私がこの若い兵士を見て、私の個人的理由によって彼を愛着したために、射ちたくないと感じたことはこれを信じる。
私は事前の決意がこの時の一連の私の心理に痕跡を止めていないため、それが私の心と行為を導いたということは認め難い。しかし遍在的な父親の感情が私に射つことを禁じたという仮定は、その時実際それを感じた記憶が少しもないにもかかわらず、それが私の映像の記憶に残るある色合いと、その後私を訪れた一つの観念を説明するという理由で、これを信ぜざるを得ないのである。>(この直後、冒頭に引用した「これが我々が心理を見詰めて見出し得るすべてである。」の一文がつづきます。)
ここで、「遍在的な父親の感情」が、米兵を射たなかった一つの大きな原因であるかも知れないという仮定が挙げられます。この感覚がわかりにくい方は、古文の『平家物語』で勉強したであろう、「敦盛の最期」の、熊谷次郎直実の心情を思い出して下さい。もちろん『俘虜記』の作者は、熊谷のように直接的な心情が米兵を射つことの禁忌だったとするのは「牽強付会」であると言っていますが、「遍在的な父親の感情」や「アメリカの母親の感謝」とは、ミンドロ島の戦場で作者の目の前にいた一人の若い米兵の生命に関するものであり、それは敦盛を殺したくなかった熊谷の心情に通じるものだと思っていただいても、差しつかえないでしょう。
<とまれかくして米兵は私を認めずに去り、私はこの青年を「助けた」という「美行」の陶酔と共に残された。>
このようにして、作者は若い米兵を射つことなく、ふたたび一人取り残されました。最後の引用部分のあとに書かれているのは、自分が彼を射たなかったことで、米兵が味方との戦闘に加わり、「僚友の負担が増した」ことに対する反省の意です。
このあと作者は自殺を図り、失敗して、米軍の俘虜となります。そして生還した後、ミンドロ島での記憶を「映像」の面から検証して、このように詳細な心理の分析、描写をなしたのが、『俘虜記』という作品の、教科書に掲載されている部分です(新潮文庫版『俘虜記』では、「捉まるまで」として、収められています)。
本稿の第1回では、高校生のみなさんの内容理解の手助けとなるであろう時代背景など、そしてこの第2回では、心理描写のうち、特にわかりにくいのではないかと思われる箇所を、全体の流れの理解を助けることを意図して解説してみました。少しでもお役に立てば幸いです。また、ご質問などありましたら、メールでご遠慮なくお寄せ下さい。
*1 マキャベリズム・・・マキャベリ主義。目的のためには手段を選ばない権謀術数主義。
*2 シニスム・・・フランス語。英語のシニシズムのこと。ものごとを冷笑的に眺める見方。
語注はいずれも、東京書籍『現代文』[現文548]によります。また『俘虜記』原文の引用は、同教科書と新潮文庫版『俘虜記』の双方によっています。
◇内容についてより詳しく知りたい方、他作品でも、国語の勉強についてご相談のある方は、お気軽に下記(言問学舎・小田原)までご連絡下さい。
TEL03-5805-7817 E-mail hyojo@kotogaku.co.jp