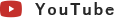- HOME >
- 高校生の現代文テスト対策 大岡昇平『俘虜記』①
高校生の現代文テスト対策 大岡昇平『俘虜記』①
読者の方からリクエストをいただき、大岡昇平の『俘虜記』に関する考察・解説を試みようと思います。ただし、今学期の期末テストに合わせるため、取り急ぎ高校の教科書に掲載されている範囲について、今回2回にわたって解説し、追って全体の考察を進めたいと思います。ご承知いただければ幸いです。
では、まず今回の1回目として、時代背景の面と、それゆえ読み取れる作中の描写について、見ていきましょう。
まず、作品に描かれているのは、1944年(昭和19年)から1945年(昭和20年)にかけての、フィリピンのミンドロ島の状況です。みなさんご存じと思いますが、1941年(昭和16年)12月8日に、日本はアメリカに宣戦布告し、太平洋戦争がはじまりました。ハワイの真珠湾と同時に、マレー半島などにも日本陸軍が進出、フィリピンも当初からの攻略対象で、1942年(昭和17年)5月にアメリカ軍が降伏しています。この時のアメリカ側のフィリピン防衛軍の司令官が、戦後GHQの最高司令官として日本占領を指揮した、マッカーサー将軍でした(フィリピンの戦いでは、途中でオーストラリアへ脱出)。
また、当時日本の憲法は「大日本帝国憲法」で、男子は満二十歳になると、徴兵検査を受け、軍隊に入る義務がありました。さらに戦前は、海軍兵学校、陸軍幼年学校、陸軍士官学校などに入り、「職業軍人」として出世することが、立身出世の一つの道、というよりも多くの少年たちにとって「王道」であった時代です。ただし『俘虜記』の作者である大岡昇平は、「昭和初期に大人となったインテリの一人」(新潮文庫版『俘虜記』中、「タクロバンの雨」)であり、そのような道を歩んだのではありません。
1943年(昭和18年)10月には、それまで徴兵を猶予されていた大学生が、「学徒出陣」として陸軍・海軍へ入隊させられるようになりました。当初は優勢に勝ち進んでいた日本軍でしたが、1942年(昭和17年)6月以降は苦戦に転じ、将兵の数も足りなくなって行ったのです。
「補充兵」とは、こうした時局の中で最前線の兵員数に不足が生じ、その補充のために、作者が「35歳」という年齢で応召したように、最前線の兵士としては適齢期を過ぎた年齢で、かつ最下層の階級として「補充」された、軍の中でも重きを置かれない存在の兵士だったようです。「補充兵」という言葉自体が、その性質を物語っています。
もう一つ、その時代のことをお伝えしておきたいと思います。教科書にも載っている本文中、作者自身が、学生の時実弾射撃の成績が良く、射とうと思えば無警戒の状態で近づいてきた米兵を射つことができたはずだ、むしろそれが自然だった、という内容の記述があります。当時の学校では軍事教練が全員に課されていて、先の学徒出陣も、若く壮健で、子どもの時から軍事教練を受けて来たたくさんの若者に、目が向けられたという背景があるのです。作者も軍事教練で実際に銃を撃ち、その扱いには自信を持っていたということですが、これは当事者の感覚として、事実なのだと考えられます。
一部の教科書には掲載されているであろう末尾の方に、「最後の一戦」という言葉があります。これは文字通り、前に「俺がうまく逃がしてやる」(おそらく教科書では非掲載)と言った伍長(陸軍のみにある階級で、下士官の最下位。「軍曹」がその一つ上です)が、「戦って死ぬ」ことを表現した言葉です。『俘虜記』の「俘虜」という言葉、またその存在そのものが、当時の日本軍の「教え」としてはゆるされないもので、「生きて虜囚の辱(はずかし)めを受けず」というようなスローガンのもと、実際に民間人までもが、自ら死を選んだケースもありました。「最後の一戦」とは、そのような背景から、敵につかまるぐらいなら華々しく戦って死ぬのだ、という意味を持っていたのだと、理解して下さい。
これで第1回を終わりとさせていただき、次の第2回で、心理面についての考察を致します。第2回は、一両日中に掲載させていただきます。
◇内容についてより詳しく知りたい方、他作品でも、国語の勉強についてご相談のある方は、お気軽に下記(言問学舎・小田原)までご連絡下さい。
TEL03-5805-7817 E-mail hyojo@kotogaku.co.jp