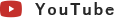- HOME >
- 高村光太郎『レモン哀歌』解題 その②
高村光太郎『レモン哀歌』解題 その②
前回、上高地に光太郎をたずねた時のことに関して、「長沼智恵子」という智恵子の旧姓でのフルネームを記しました。亡くなられた際は、もちろん高村智恵子です。
当たり前のことを言うようですが、光太郎と智恵子のことを語る時、この「姓」の問題は、現代のわれわれが考える「当たり前」ではなかったのだということを、お話しします。
事実的な結論から先に言うと、智恵子が高村の籍に入ったのは昭和8年のことであり、上高地行のあと結婚生活に入ってから、19年の歳月を経たのちのことでした。
このことの実相をお話しする前に、まず光太郎の生い立ちと、父高村光雲との関係に、触れる必要があります。
光太郎の父高村光雲は、木彫家であり、東京美術学校(のちの東京芸術大学)の教授や帝室技芸員を務めた大家でした。長男の光太郎は、当然のようにその跡を継ぐことを求められ、十代の頃から木彫の技術を学びますが、やがてアメリカ、次いでフランスへわたり、近代の芸術と人間の自我の覚醒を知ったことから、古い伝統を守る父の芸術観との相克に悩むようになります。
いっぽうでは新しい芸術で古い価値観を打破しようとする気概に燃えながら、いっぽうでは父の権威から逃れることのできない自己のありようを突きつけられ、また金銭を得るために芸術上の妥協をすることのできない「業」(『へんな貧』など)を負ってもがき苦しんでいた光太郎の精神を洗いきよめ、「私を全部に解してくれ」(『人類の泉』)たのが、智恵子でした。
そして智恵子もまた、前回ご紹介した通り、「新しい女性」としてゴシップを書かれるような古い世間の価値観に抗しながら、油絵を志し、真に自分らしい生き方と芸術の至上とを追い究めようとする、強い意志を持った女性でした。そんな二人は結婚に際し、入籍という世間尋常の手続きをとることを潔しとしませんでした。形式はなくとも実質を優先することが、光太郎と智恵子という、この世でお互いだけを唯一無二の存在として認め合った二人にとって、自然かつ必然のことだったのです。
ただ、こうした光太郎と智恵子の結婚は、光太郎の父や母にとっては、彼らがずっと望んで来たものとはかけはなれた結婚であると言わざるを得ませんでした。光太郎が父に従順で優秀な跡取りとなり、さらに可愛い後継ぎの孫を得ることが、両親の望みだったのです。光太郎は、そうした両親の思ったままのレールに乗ることは拒みながらも、内心では父や母にすまないという思いを持ちつづけていました。そして智恵子は、最初に服毒自殺を図った際の遺書に、義父光雲への詫びの言葉を、書き連ねていたとのことです。
そんな経緯を有する光太郎と智恵子の結婚生活において、入籍という手段を光太郎がとったのは、智恵子の病状が悪化して、もしも光太郎自身の身に万一のことがあった時、病める智恵子が寄る辺のない身になってしまうことを案じたからです。そして昭和10年に書かれた『人生遠視』で、作品中はじめて智恵子のことを「妻」と呼び、智恵子の没後2年を経て書いた『智恵子の半生』(智恵子追悼の散文)では「妻智恵子が南品川ゼームス坂病院の十五号室で・・・」と述べた、その「妻」という言葉にこめられた慟哭を思う時、智恵子を籍にも入れて「妻」として見送った光太郎の思いが、せつせつと身に迫って来ることを感じます。
このような背景をも、『レモン哀歌』を読むに当たって、押さえていただきたいと思います。そしてぜひ、『智恵子の半生』もあわせて読むことをおすすめします。その中にこそ、光太郎の智恵子への思いが余すことなく書かれていますから。
※YouTube上で、「レモン哀歌」を朗読しております。下記リンクよりご覧下さい。
https://www.youtube.com/watch?v=7MbHWkIbJ6I&feature