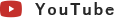- HOME >
- 高校生の現代文テスト対策 芥川龍之介『羅生門』④下人の心理2
高校生の現代文テスト対策 芥川龍之介『羅生門』④下人の心理2
楼上へ上がる梯子に最初の一歩をふみかけた時、下人は、この門の上には死体しかあるまいと、考えていました。ところが数分後には、「猫のように身をちぢめて」、様子をうかがい、「やもりのように足音をぬすんで」、梯子を上ってゆくのです。
ここのところは、よく注意して読みましょう。下人は二、三段上ったところで、「上ではだれか火をとぼして、しかもその火をそこここと、動かしているらしい」ことに気づいたのです。そして「この雨の夜に、この羅生門の上で、火をともしているからには、どうせただの者ではない」と判断して、そっと息をひそめ、相手に気づかれないように、梯子を上り切りました。
小説のディテール(細部)の味わいとしてみると、梯子を二、三段上ってだれかが上にいることに気づいたことと、「それから、何分かの後」に、梯子の中段で様子をうかがっている下人の描写とが、時間的な順序とは逆に描かれているあたり、とても巧みです。順に描くより、この方が楼上の様子をさぐる下人の緊張感に、より迫真性がともなうからです。
また、楼上でだれかが火を使っていることに下人が気づく次の描写も、芥川らしい緻密で鬼気せまる表現が秀逸です。「これは、その濁った黄色い光が、隅々に蜘蛛の巣をかかげた天井裏に、揺れながら映ったので、すぐにそれと知れたのである。」
さて、楼上にうごめく人間の正体は老婆でしたが、はじめはその老婆が何をしているかわからないため、下人は、「六分の恐怖と四分の好奇心」で、老婆のすることを見つめていました。そして、老婆が死体の髪の毛を抜いているのだということがわかると、下人の心から、少しずつ恐怖が消えていきます。
なぜ、「髪の毛を抜いている」ことがわかると、恐怖が消えるのでしょうか。
それは、想像の埒外(らちがい)にあった恐怖の対象が、あたりまえの人間の所作(しょさ=すること)の範疇に、おさまってくるからです。はじめ下人が楼上の人の気配にひどく警戒したのは、「どうせただの者ではない」その相手が、自分にとって危険な対象であるか否かが、わからなかったためです。それが老婆であると判明し、今度は、その老婆が「いったい何者なのか」ということが、「六分の恐怖」となり、女の死骸をのぞきこむその様子から、「何をするのか」について、「四分の好奇心」を抱いたわけです。
ところが、死体から髪の毛を抜く、というのは、異常な行動ではあっても、たとえばいきなり大口を開いて死体の顔に食らいつく、などという行為とくらべれば、あたりまえの範疇の行動です。だからこそ、老婆の前に立ちはだかって太刀を抜いて問いつめたあと、「この髪を抜いてな、この髪を抜いてな、かつらにしょうと思うたのじゃ。」という答えが平凡であることに、下人は失望したのです。
このあたりの下人の心理の動きを、<読解シートの⑧>では、つぎのようにまとめました。
◎「老婆」に対する「下人」の感情の移り変わりとして、次の要素を正しく並べよ。
(解答)好奇・恐怖 → 怒り(正義感) → 満足感 → 侮蔑 → 加害意識
2番目の「怒り」とは、「死体の髪を抜く」という「悪」への「怒り」ですね。それに対する老婆の言い分を集約すると、こうなります<読解シートの⑦>
死体の髪を抜くことはわるいことかも知れないが、それをしなければ自分が飢え死にするのだからしかたがない。(現に、今髪を抜いていた女は、生きている間に蛇の肉を干し魚と偽って売っていた。それも飢え死にしないための手立てだったのだから、自分もこの女も同類だ)。
また、「満足感」は、老婆をねじ倒し、太刀をつきつけて、「この老婆の生死が、全然、自分の意思に支配されているということを意識した」際の、「ある仕事をして、それが円満に成就した時の、安らかな得意と満足」です。ここに至るまで、下人は「悪」に対する「憎悪」(読解シートでは、理解しやすく、かつ多角的にとらえるように「怒り」としています)でいっぱいだったのです。
そして、下人の心には、悪に対する憎悪とともに、老婆に対する侮蔑の心が生まれ、「自分が生きるために死者の髪を抜いてかつらにする」言い分を聞きとると、さらに大きく、心理状態が転回します。
その部分を最後のまとめとして、次回完結と致します。